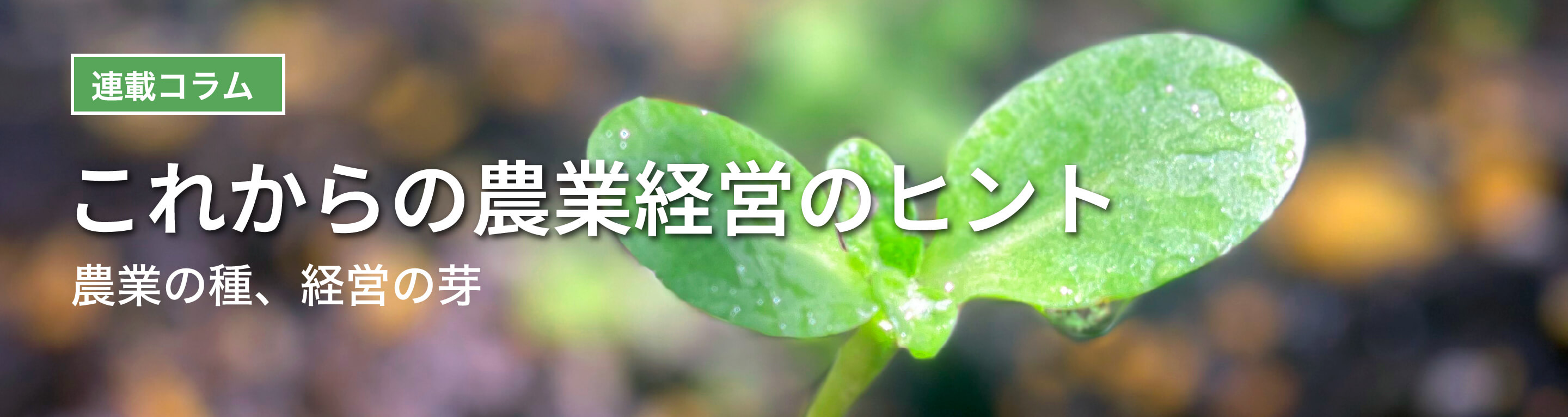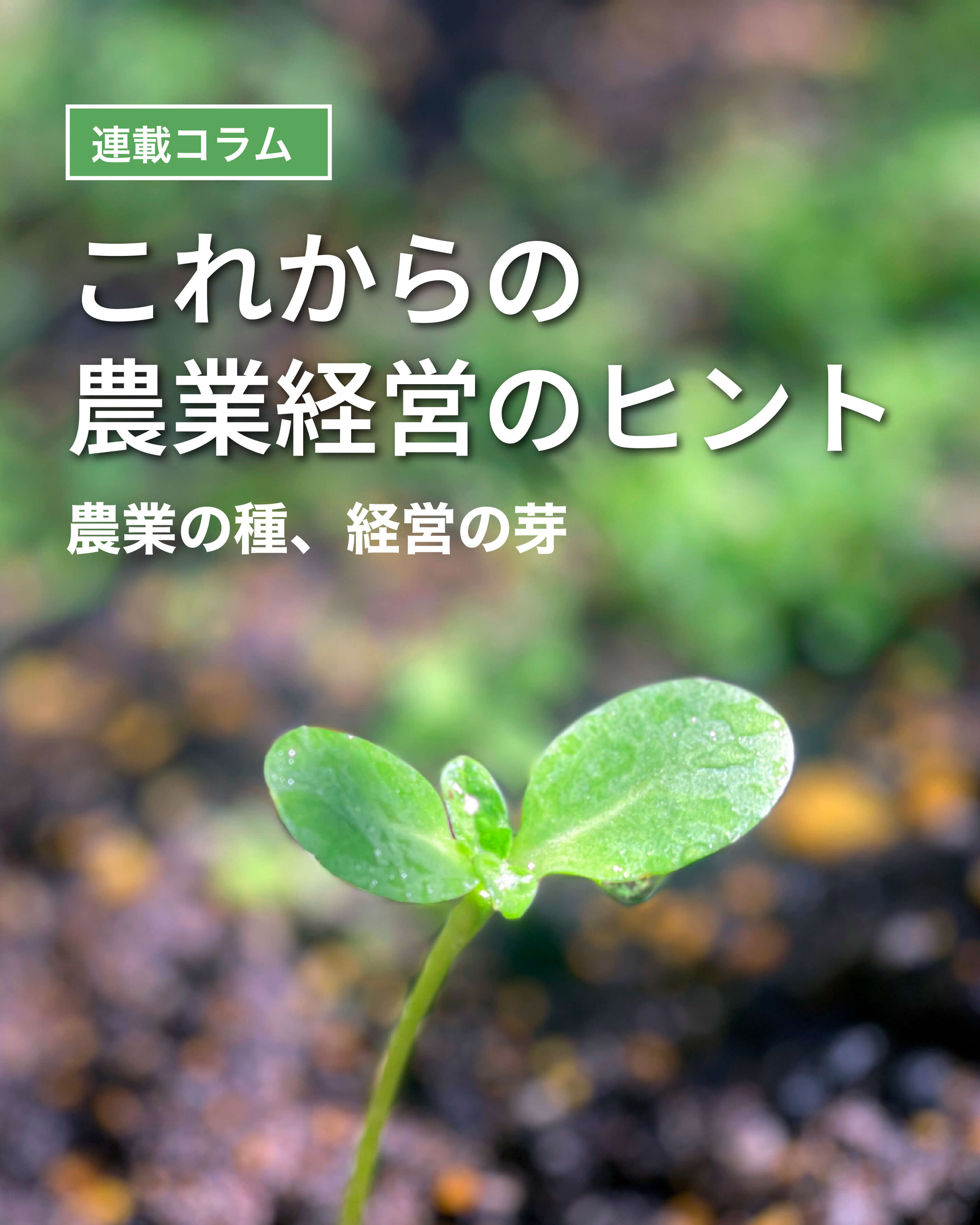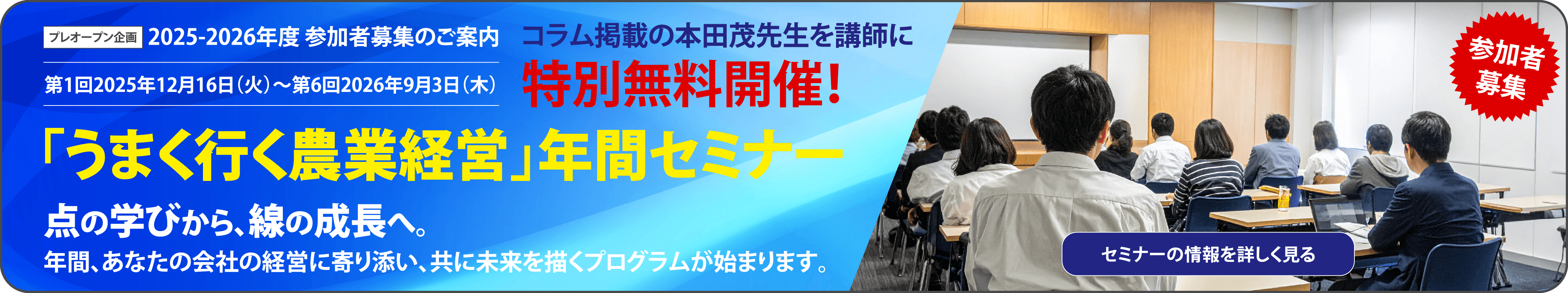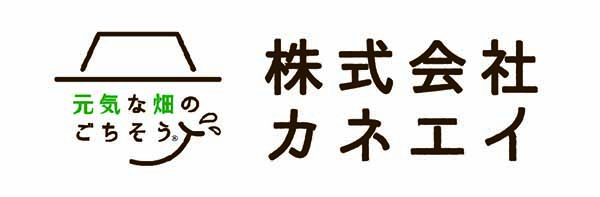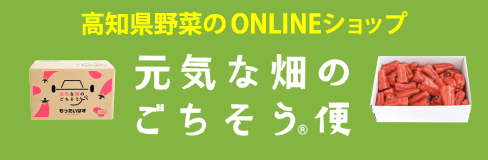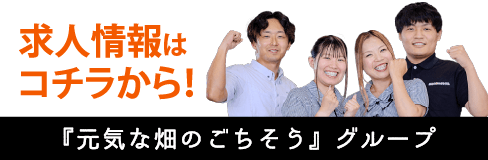これまで「決算書の見方」や「お金の流れ(キャッシュフロー)」など、数字を読み解く方法について解説してきました。決算書からは経営の成果や課題が見えてきますが、その数字が生まれる背景には、経営者の「判断」の積み重ねがあります。
今回は視点を変え、多くの農業経営者が陥りがちな「思考のパターン」、いわば経営の落とし穴について解説します。様々な経営を見てきた中で、経営が悪化する要因には共通するパターンがあると感じています。耳の痛い話に聞こえるかもしれませんが、ご自身の経営を客観的に見つめ直すきっかけとして、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
落とし穴1:急激な規模拡大
補助金などを活用し、ハウスの新設や農地拡大によって一気に規模を2倍にする。こうした急激な規模拡大は、高い確率で経営を圧迫する要因となります。
規模が大きくなると、これまで家族や熟練スタッフで管理できていた範囲を大きく超えてしまいます。新しい人材を増やしても、育成が追いつかず、結果として全体の管理が行き届かなくなります。それに伴い、チーム内のコミュニケーション不足や雰囲気の悪化といった問題も発生し、全体の生産効率が低下していくのです。
もちろん、投資による減価償却費の負担が増え、赤字に陥りやすくなるという直接的な影響もあります。しかし、より深刻なのは、支出が先行して増える中で、管理不足による病気の発生や収量減少が重なり、資金繰りが一気に悪化する悪循環です。
一般の製造業では、規模の拡大が効率化に直結しますが、農業、特に人の手と経験が重要な園芸では、その常識が通用しにくいのです。規模拡大そのものを否定しているわけではありません。「急激すぎる」拡大が問題なのです。一度大規模な投資をしてしまうと後戻りが難しく、厳しい状況のまま事業を継続せざるを得ない状況に陥ってしまいます。
落とし穴2:急激な方針転換
栽培経験のない新しい品目に、いきなり1ヘクタール単位で転換する。長年続けてきた栽培方法を、全栽培面積で同時に新しいやり方に変える。このような急激な方針転換も、経営を悪化させる典型的なパターンです。
農家の方には、「これだ」と思い込むとゼロか百かで判断し、全てを急激に変えてしまう傾向が見られます。外から見ている立場としては、「まずは1割程度の面積で試してみて、成果を見ながら翌年以降に面積を増やしていく」という段階的なアプローチを考えてほしいのですが、「こうと決めたら全力を注ぎたい」という想いが勝ってしまうようです。
その結果、わずかな環境変化で予期せぬトラブルが多発し、対応に追われるうちに収量が大幅に減少。家族やスタッフとの間に対立が生まれることもあります。また、「一度変えたら後戻りはしたくない」という意地から、うまくいかなくても元の方法に戻すことを考えず、全員が我慢を続ける「我慢大会」のような状態に陥ってしまうことも、共通した特徴です。
落とし穴3:無理な雇用
通年雇用できるほどの売上規模がないにもかかわらず、無理に正社員を雇用してしまうケースです。繁忙期だけでなく閑散期にも固定給を支払うことは、経営を確実に悪化させます。
背景には、補助金の要件に通年雇用が含まれていることや、地方では人材確保が難しく「この機会を逃すと次はない」という焦りが挙げられます。縁あって応募してくれた人材を逃したくないという気持ちは痛いほど分かります。しかし、その焦りが冷静な判断を曇らせてしまうのです。
こうした無理な雇用から生まれる経営者の不安は、必ずスタッフにも伝わります。最初は良好だった関係も、経営者が「こんなはずではなかった」「もっと働いてくれると思った」と感じ始めると、周年雇用そのものが精神的な重荷となっていきます。
また、スタッフの数が増えることで、人間関係の問題も複雑化します。一部のベテランスタッフが派閥を作り、自分の意に沿わない人材を排除するようになると、人の入れ替わりが激しくなります。経営者がその原因に気づいていても、「仕事ができるあの人がいなくなっては困る」と、何も言えなくなってしまうのです。
落とし穴4:数字を見ない契約取引
近年、市場外流通が増え、取引先との直接契約も一般的になりました。価格が安定するメリットは大きいですが、その裏には危険な罠が潜んでいます。
それは、自社の生産原価を正確に把握しないまま、取引先の言い値で契約してしまうケースです。私が原価計算をして「この契約単価では赤字です」と助言しても、「規格が簡素化されて手間が省けるから大丈夫」といった理由で、現実から目を背けてしまう方を多く見てきました。
こうした無理な契約が起きてしまう背景には、主に3つの心理的要因が考えられます。
1.手間が省けることへの過大評価
選別作業などが楽になると、単価が安くても得をしたように感じてしまう。
2.原価意識の欠如
そもそも自社の原価を知らないため、提示された単価に疑問を持つことができない。
3.価格交渉への恐怖
過去に値上げを要請して取引を止められた経験がトラウマになり、交渉そのものを恐れてしまう。
商談に長けた取引先にとって、経験の少ない農家からの価格交渉に対応することは、残念ながら容易なことです。しかし、その一度の失敗が原因で、赤字の契約を続けたまま経営を悪化させてしまう場面は後を絶ちません。
いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した4つの落とし穴には、共通する背景があるように思います。それは、「今しかない」という焦りや、「自分一人で何とかしなければ」という思い込みです。
もし、ご自身の経営に少しでも思い当たる節があれば、一度立ち止まり、客観的に状況を見つめ直す時間を作ってみてください。そして、ご家族や信頼できるスタッフ、あるいは我々のような外部の専門家と一緒に、決算書を広げて話し合ってみてください。
決算書は、過去の成果を映すだけでなく、未来の羅針盤ともなります。数字に基づいた冷静な対話こそが、これらの「落とし穴」を回避し、持続可能な経営を築くための最も確実な一歩となるはずです。