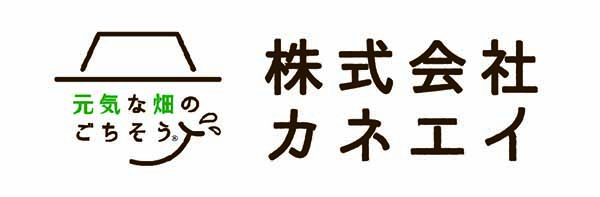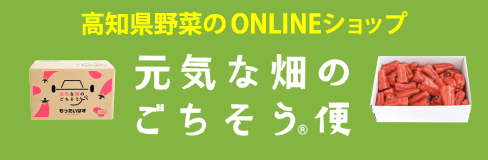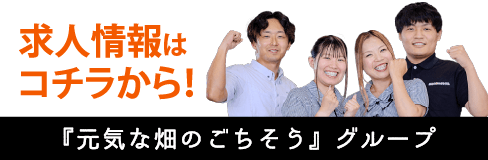皆さま、ご機嫌いかがでしょうか?『元気な畑のごちそう』株式会社須崎青果 代表取締役の市川義人です。
いつも須崎青果のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
さて、今年の1月に当ホームページでお知らせした「出荷奨励金制度」につきまして、生産者の皆様から様々なお問い合わせやご意見を頂戴しております。特に「なぜ一部の生産者だけが対象なのか?」「なぜ基準があるのか?」といったご不安の声があることは、私どもも真摯に受け止めております。
今回のブログでは、この制度が一部の方への「特別ボーナス」ではないこと、そして、この市場に関わる私たち全員の未来を守るための「市場共有の確保」という、より大きな目的のためにあることを、私たちの調査と想いを交えてご説明いたします。
1.全国の市場が取り組む「出荷奨励金」という仕組み
まず、この出荷奨励金制度は、私たち須崎青果が独自に考えたものではなく、全国の卸売市場で広く導入されている、市場の活力を維持するための重要な仕組みです。
私たちが全国の事例を調査した結果から、多くの市場で共通の目的とルールがあることがわかりました。
目的は「安定供給」
全国の市場が、天候や時期に左右されやすい青果物の「安定的供給の確保」を最大の目的として制度を設けています。例えば、徳島市中央卸売市場でも、これが第一の目的として明記されています。
対象は「協力体制」
多くの市場では、JAや出荷組合といった「組織化された出荷者」を対象としています。宇都宮市中央卸売市場の例のように、皆で協力して規格を統一し、計画的に出荷する体制を奨励しています。これにより、市場全体の取引が効率的になります。
条件は「市場への貢献」
一般的に、ただ出荷するだけでなく、産地で品質やサイズを揃える(選別・選果)など、市場の信頼性を高め、コスト削減に繋がる出荷方法が評価されます。これは、市場というプラットフォーム全体の価値を高める行為だからです。
基準は「客観性」
奨励金の交付率には、出荷額に応じて段階的な設定を設けるのが一般的です。福岡市や札幌市の市場でも、出荷規模に応じた公平なインセンティブとなるよう、客観的な基準が設けられています。
このように、出荷奨励金とは、市場の機能を強化し、その利益を皆に還元していくための、全国共通の戦略的な仕組みなのです。
2.私たちが目指す「市場共有の確保」とは
では、私たち須崎青果がこの制度で目指す「市場共有の確保」とは何でしょうか?
それは、この高知県西部地方卸売市場が、10年後、20年後も、この地域の生産者の皆様にとって最も信頼でき、安定した販売先であり続けることに他なりません。
もし、市場に並ぶ商品の量や品質が不安定になれば、競売に参加する買い手の販売力の低下につながります。そうなれば、価格は不安定になり、結果として生産者の皆様全員の収入に影響が及びます。
出荷奨励金制度は、こうした事態を防ぎ、市場の信頼性とブランド力を高めるための「投資」です。高品質で安定した商品が集まる魅力的な市場を維持することで、生産者の皆様全員の販路という「共有財産」を確保していく。それが、この制度に込めた私たちの想いです。
3.ご理解いただきたい、制度の「仕組み」と「理由」
この大きな目的があるからこそ、制度には一定のルールが必要となります。
「インセンティブ」である理由
この制度は、市場の安定と効率化に繋がる特定の行動(優良品の選別、計画的な共同出荷など)を「奨励」するためのものです。もし、どのような出荷に対しても一律に奨励金をお支払いすると、それは単なる値引きと同じになり、品質や出荷体制の向上を促すという本来の目的が失われてしまいます。
「基準(線引き)」がある理由
「500万円以上」といった基準は、生産者の皆様をふるいにかけるためにあるのではありません。市場の安定に特に大きな貢献をいただいている状態を、誰もが納得できる客観的で公平な指標で判断するために設けています。これは他県の市場の事例を参考にし、当市場の実情に合わせて慎重に決定したものです。
最後に:未来に向けたパートナーとして
この出荷奨励金制度は、私たちと生産者の皆様が、未来に向けたパートナーとして、共にこの市場を育て、守っていくための約束です。
一部の方への「特別ボーナス」ではなく、市場という皆様の「共有財産」の価値を高めるための仕組みであることを、どうかご理解いただけますと幸いです。
今後とも、皆様との対話を大切にしながら、より良い市場づくりに邁進してまいります。変わらぬご協力とご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。